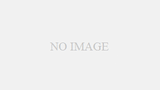血液透析の基礎知識完全ガイド
透析原理から副作用まで臨床工学技士が徹底解説
現役臨床工学技士による解説
•
2025年版最新情報
はじめに
血液透析は、腎機能が著しく低下した患者さんの生命を支える重要な治療法です。本記事では、現役臨床工学技士の立場から、血液透析の基本的な仕組みから実際の治療で使用される医療機器、治療スケジュール、注意すべき副作用まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
これから透析治療を始める患者さんやそのご家族、医療従事者を目指す学生の方々にとって有益な情報をお届けします。
👨⚕️ 執筆者プロフィール
私は臨床工学技士として透析業務に28年間従事し、腎疾患専門医療チームの一員として多くの患者さんの治療に携わってきました。
透析治療の準備風景 – 臨床工学技士として28年間携わってきた透析装置の実際の操作画面
ADPKD患者としても、PKD1遺伝子変異による発症で45歳で診断を受け、現在はeGFR 45ml/min/1.73m²を維持しながら経過観察中です。医療従事者かつ当事者という二重の視点から、信頼できる情報をお伝えします。
血液透析の原理
透析の基本メカニズム
血液透析は、主に「拡散」と「限外ろ過」という2つの物理現象を利用して、健康な腎臓の働きを代行します。
拡散(Diffusion)
原理:濃度の高い方から低い方へ物質が移動する現象
役割:血液中の老廃物(尿素、クレアチニンなど)を透析液へ移動させる
例:砂糖を水に入れると全体に広がるのと同じ原理
限外ろ過(Ultrafiltration)
原理:圧力差を利用して水分を除去する現象
役割:体内に蓄積した余分な水分を取り除く
例:コーヒーフィルターで水分を通すのと同じ原理
半透膜の役割
血液透析では、ダイアライザー内の半透膜が重要な役割を果たします。この膜は、小さな老廃物や水分は通しますが、血球やタンパク質などの大きな成分は通さない特殊な構造になっています。
透析で使用する主要な物品
ダイアライザー(人工腎臓)
ダイアライザーは「人工腎臓」とも呼ばれ、腎臓の糸球体の働きを代行する最も重要な装置です。
構造
- 細いストロー状の透析膜を約1万本束ねた構造
- 内側を血液、外側を透析液が流れる
- 有効膜面積は1.0〜2.5㎡程度
膜の種類
- 合成高分子膜:生体適合性が高い
- セルロース系膜:従来から使用される膜
- 患者さんの状態に応じて選択
透析回路(血液回路)
血液を体外に取り出し、ダイアライザーを通して再び体内に戻すための管路システムです。
脱血側回路
患者さんから血液を取り出す側
ダイアライザー
血液浄化を行う部分
返血側回路
浄化された血液を体内に戻す側
主要な構成部品
- チャンバー(血液の泡を除去)
- 圧力モニターライン(圧力監視)
- サンプルポート(採血用)
- 抗凝固剤注入ライン
穿刺針
シャント(血管アクセス)に挿入して血液の取り出しと返血を行うための針です。
17G(17ゲージ)
- 外径:約1.4mm
- 特徴:標準的なサイズ
- 適用:一般的な患者さん
- 血流量:150-250ml/分程度
16G(16ゲージ)
- 外径:約1.6mm
- 特徴:17Gより太い
- 適用:高血流量が必要な場合
- 血流量:200-300ml/分程度
ポイント:針が太いほど血流量を多く確保できますが、穿刺時の痛みや血管への負担も大きくなります。患者さんの血管の状態や透析効率を考慮して選択されます。
抗凝固剤
血液が体外循環中に凝固(固まる)することを防ぐために使用される薬剤です。透析回路から持続的に注入されます。
ヘパリン
- 使用対象:出血傾向のない患者
- 特徴:最も一般的
- 半減期:約1時間
- メリット:安価で効果的
ナファモスタット
- 使用対象:出血傾向のある患者
- 特徴:短時間作用型
- 半減期:約8分
- メリット:安全性が高い
低分子ヘパリン
- 使用対象:出血リスクのある患者
- 特徴:中程度の作用時間
- 半減期:約2時間
- メリット:使用量が少ない
医師による選択:患者さんの出血リスク、手術歴、併用薬などを総合的に判断して、最適な抗凝固剤が選択されます。抗凝固剤の詳細については、今後別のブログ記事で詳しく解説予定です。
一般的な透析スケジュール
標準的な透析パターン
週3回
4時間
12時間
典型的な週間スケジュール
透析日(4時間)
休息日
透析日(4時間)
休息日
透析日(4時間)
なぜ週3回、1回4時間なのか?
健康な腎臓は24時間365日働き続けています。この腎機能を週3回の透析で代替するため、十分な透析効率を得るには最低限の時間が必要です。
- 透析効率:十分な老廃物除去のため
- 水分除去:中2日で蓄積した余分な水分の安全な除去
- 身体への負担:急激な変化を避けた緩やかな浄化
- 生活の質:日常生活との両立
個別調整について
標準は「週3回・1回4時間」ですが、以下の要因により個別に調整されることがあります:
- 患者さんの体格・体重
- 残存腎機能の程度
- 心臓・血管の状態
- 透析導入からの期間
- 血管アクセスの状態
- 生活スタイル・就労状況
- 透析効率の評価結果
- 合併症の有無
透析の副作用と注意点
血液透析は生命を維持する重要な治療ですが、いくつかの副作用や合併症が起こる可能性があります。事前に知っておくことで、適切な対処や予防が可能になります。
透析中・直後に起こりうる急性の副作用
不均衡症候群
症状:頭痛、吐き気、嘔吐、めまい、けいれん
原因:急激な老廃物除去による脳浮腫
対策:透析導入時は緩やかな設定で開始
低血圧
症状:めまい、ふらつき、冷汗、動悸
原因:急激な除水による血液量減少
対策:適切な除水速度の設定
筋肉けいれん
症状:手足の筋肉の痛みを伴うけいれん
原因:急激な水分・電解質の変化
対策:適切な透析液組成の選択
発熱反応
症状:発熱、悪寒、全身倦怠感
原因:透析液の汚染や膜との不適合
対策:厳格な水質管理と膜の選択
長期透析で注意すべき点
血管アクセス関連
- シャント狭窄・閉塞
- 感染症のリスク
- 血管痛・腫れ
- スチール症候群
全身への影響
- 骨・関節の問題
- 心血管系への負担
- 貧血の進行
- 栄養状態の悪化
副作用の予防と早期対応
医療スタッフとの連携
- 症状の早期報告
- 定期的な検査結果の確認
- 薬の副作用の相談
日常生活での注意
- 水分・塩分制限の遵守
- 適度な運動の継続
- 感染予防の徹底
定期的なモニタリング
- 透析効率の評価
- 栄養状態の評価
- 合併症のスクリーニング
まとめ
血液透析は、拡散と限外ろ過の原理を利用して腎臓の機能を代行する治療法です。ダイアライザー、透析回路、穿刺針、抗凝固剤など、多くの医療機器と薬剤が組み合わされて安全で効果的な治療が提供されています。
標準的な「週3回・1回4時間」の治療スケジュールは、透析効率と生活の質のバランスを考慮して設定されています。副作用や合併症のリスクもありますが、適切な予防策と早期対応により、多くの患者さんが安全に治療を継続されています。
透析治療について不安や疑問がある場合は、遠慮なく医療スタッフにご相談ください。患者さん一人ひとりに最適な治療を提供するため、チーム一丸となってサポートいたします。