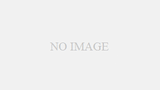腹膜透析完全ガイド
CAPD・APDの違いとPKD患者の適応【2024年最新】
腹膜透析(PD)の種類から適応、PKD特有の問題まで
医療従事者と患者さんのための実用的な完全ガイド
目次
腹膜透析とは
腹膜透析(Peritoneal Dialysis:PD)は、患者さん自身の腹膜を透析膜として利用する在宅透析療法です。血液透析のように医療機関に通院する必要がなく、自宅や職場で治療を行うことができます。
🔍 腹膜透析の基本原理
- 拡散:老廃物や電解質が濃度勾配により除去される
- 限外ろ過:透析液の浸透圧により余分な水分が除去される
- 対流:水分と一緒に中分子量物質も除去される
主な特徴
- 24時間連続的な治療
- 緩やかな老廃物除去
- 残存腎機能の保護
- 自宅での治療が可能
適応の現状
日本の腹膜透析患者数は約9,000人で、全透析患者の約3%を占めています。近年、残存腎機能保護の観点から「PD first」の概念が注目されています。
CAPDとAPDの違い
CAPD
連続携行式腹膜透析
Continuous Ambulatory PD
治療スケジュール
- • 1日2~4回のバッグ交換
- • 1回20~30分程度
- • 透析液は常に腹腔内に貯留
適応患者
- • 日中の活動に制限が少ない方
- • 手技を確実に行える方
- • 家族のサポートがある方
メリット
- • 機械不要で簡便
- • コストが低い
- • 旅行時も継続可能
デメリット
- • 日中の腹部膨満感
- • 頻繁な手技が必要
- • 感染リスク
APD
自動腹膜透析
Automated Peritoneal Dialysis
治療スケジュール
- • 夜間就寝中に自動で透析
- • 8~10時間程度
- • 日中は透析液なしまたは少量貯留
適応患者
- • 社会活動が活発な方
- • 腰痛・ヘルニアのある方
- • 日中の膨満感を避けたい方
メリット
- • 日中の自由時間確保
- • 社会復帰しやすい
- • 感染リスクが比較的低い
デメリット
- • 機械が必要
- • 電源確保が必要
- • 小分子除去が不十分な場合
CAPD vs APD 選択のポイント
ライフスタイル
仕事や学業の都合、活動時間帯を考慮
医学的要因
腰痛、ヘルニア、腹部手術歴など
居住環境
電源確保、機械設置スペースの有無
適応患者の選び方
良い適応となる患者さん
医学的適応
- 残存腎機能がある(尿量1日500ml以上)
- 心血管系合併症が少ない
- バスキュラーアクセス作成困難
- 血液透析による血圧変動が大きい
社会的適応
- 社会活動を継続したい
- 通院が困難(地理的要因)
- 自己管理能力がある
- 家族のサポートが得られる
年齢による特徴
- 小児:成長・発育、学業継続
- 成人:就労継続、妊娠希望
- 高齢者:通院負担軽減
注意が必要な患者さん
絶対的禁忌
- 腹膜機能の著明な低下
- 透析液の適切な貯留・排液が不可能
- 重篤な腹腔内癒着
- 活動性腹膜炎
相対的禁忌
- 巨大な腹部臓器(PKDなど)
- 重度の呼吸器疾患
- 腹壁ヘルニア
- 炎症性腸疾患
- 認知症・精神疾患
慎重な評価が必要
- 高度肥満(BMI > 30)
- 腹部手術既往
- 悪性腫瘍既往
- 視力障害・手指機能障害
「PD First」の概念
残存腎機能を有する患者において、腹膜透析を優先的に考慮する治療戦略です。残存腎機能の保護により、以下のメリットが期待できます:
心血管保護
体液管理改善
QOL向上
血液透析 vs 腹膜透析 詳細比較
| 比較項目 | 血液透析(HD) | 腹膜透析(PD) |
|---|---|---|
| 治療場所 | 医療機関 | 自宅・職場 |
| 治療頻度 | 週3回、4-5時間/回 | 毎日、24時間連続 |
| 通院回数 | 週3回 | 月1-2回 |
| 血管アクセス | 必要(シャント等) | 不要 |
| 残存腎機能 | 急速に低下 | 緩やかに保持 |
| 食事制限 | 厳格 | 比較的緩やか |
| 水分制限 | 厳格 | 比較的緩やか |
| 社会復帰 | 制限あり | 制限少ない |
| 初期費用 | 高い | 比較的低い |
| 感染リスク | 血流感染 | 腹膜炎 |
血液透析が適している場合
- 残存腎機能がほとんどない
- 腹膜機能が低下している
- 医療機関でのサポートを希望
- 自己管理に不安がある
- 家族のサポートが困難
- 腹膜透析の禁忌がある
腹膜透析が適している場合
- 残存腎機能がある
- 社会活動を継続したい
- 通院が困難
- 自己管理能力がある
- 血管アクセス作成困難
- 心血管系合併症がある
PKD患者特有の問題と対策
ADPKD患者における腹膜透析の特殊事情
常染色体優性多発性のう胞腎(ADPKD)患者では、腎臓の著明な腫大により腹腔内スペースが制限されるため、腹膜透析の適応に特別な配慮が必要です。
PKD患者の腹膜透析における問題点
腹腔内スペースの制限
- 巨大腎による物理的圧迫
- 透析液貯留量の制限
- 透析効率の低下
- 腹部膨満感の増強
呼吸器系への影響
- 横隔膜の挙上
- 呼吸困難の増強
- 睡眠時無呼吸の悪化
- 運動耐容能の低下
体重・栄養管理
- 早期満腹感による摂食不良
- タンパク質・エネルギー摂取不足
- 透析液からの糖質吸収
- 体重増加の管理困難
PKD患者への対策・工夫
透析処方の調整
- 透析液貯留量の減量(1.5-2.0L程度)
- 交換回数の増加
- APDの積極的検討
- CCPD(連続性サイクリック腹膜透析)の利用
医学的管理
- 定期的な腎容積測定
- 呼吸機能の評価
- 栄養状態のモニタリング
- 腹膜機能検査の頻回実施
併用療法の検討
- 早期のPD+HD併用療法導入
- 腎摘出術の検討
- サムスカ®による腎容積制御
- 腎移植への早期移行
PKD患者における腹膜透析の実際
一般的な腎容量での
透析液貯留量の目安
巨大腎(>3,000ml)での
透析液貯留量の目安
PKD患者でも
腹膜透析が実施可能
腹膜透析の限界と対策
時間的限界
腹膜機能の経時的変化
- 腹膜劣化:長期間の透析液暴露により腹膜が硬化
- 限外ろ過能低下:水分除去能力の段階的減少
- 溶質除去能低下:老廃物除去効率の悪化
- 平均継続期間:5-8年程度で他療法への移行が必要
感染リスク
腹膜炎のリスク
- 発症頻度:0.3-0.5回/患者年
- 主な原因:手技不良、出口部感染
- 重篤例:腹膜硬化、透析離脱の原因
- 予防:適切な手技教育、清潔操作の徹底
透析効率の限界
除去能力の制限
- 小分子除去:血液透析より劣る
- リン除去:特に不十分になりやすい
- 体重増加:透析液の糖分吸収
- 残存腎機能依存:腎機能低下で透析不足
患者要因による限界
継続困難となる要因
- 手技困難:視力低下、手指機能障害
- 認知機能低下:手技の理解困難
- 家族サポート減少:介護者の高齢化
- 居住環境変化:施設入所等
腹膜透析の限界を迎えたときの対策
血液透析への移行
- • バスキュラーアクセス作成
- • 段階的移行
- • PDカテーテル抜去
併用療法
- • PD + HD併用
- • 段階的透析強化
- • 残存PD機能活用
腎移植
- • 早期からの検討
- • ドナー探索
- • 移植登録
PD+HD併用療法(ハイブリッド透析)
併用療法とは
腹膜透析単独では十分な透析効果が得られない場合に、週1-2回の血液透析を追加する治療法です。腹膜透析の利点を活かしながら、透析不足を補うことができます。
一般的な併用パターン
週5日:腹膜透析 + 週1日:血液透析 + 週1日:休み
併用療法の適応
医学的適応
- PD単独でKt/V < 1.7
- 週クレアチニンクリアランス < 60L
- 体液過剰の改善困難
- リン管理不良
- 残存腎機能の低下
患者要因
- 体格が大きい(高いBSA)
- 高い代謝率
- 腹膜機能の低下
- PKDによる腹腔内スペース制限
社会的要因
- PD継続への強い希望
- 就労継続の必要性
- HD単独への抵抗感
- 家族の支援体制
併用療法のメリット
透析効率の向上
- 小分子量物質除去の改善
- 中・大分子量物質の効率的除去
- リン除去能の向上
- 総合的な透析adequacyの改善
体液管理の改善
- 確実な除水
- 体重管理の容易化
- 心血管負荷の軽減
- 血圧管理の改善
QOLの維持
- 在宅透析の継続
- 社会活動の維持
- 通院頻度の最小化
- 自立性の保持
併用療法の実際のスケジュール例
or
APD
or
APD
4時間
or
APD
or
APD
or
APD
腹膜透析
血液透析
透析なし
併用療法の注意点
医学的管理
- バスキュラーアクセスの管理
- 感染リスクの増加
- 適切な透析量の評価
- 電解質バランスの調整
患者負担
- 通院頻度の増加
- 治療時間の延長
- 医療費の増加
- 複雑な管理の必要性
まとめと今後への提言
腹膜透析選択の重要ポイント
患者選択
- 残存腎機能がある患者に積極的適応
- 社会活動継続希望者への配慮
- 個々の生活環境の詳細な評価
- 家族サポート体制の確認
治療法選択
- CAPD vs APDの適切な選択
- 早期からの併用療法検討
- 定期的な治療効果評価
- 他療法への移行タイミング
PKD患者への特別な配慮
早期評価
腎容積、腹膜機能の詳細評価による適応判定
処方調整
腎容積に応じた透析液量・回数の最適化
併用検討
早期からのPD+HD併用療法の検討
医療従事者への提言
情報提供の充実
- 腹膜透析の選択肢を必ず提示
- CAPD・APDの違いを丁寧に説明
- 患者のライフスタイルに応じた提案
- 将来の治療計画も含めた情報共有
継続的サポート
- 定期的な治療効果評価
- 合併症の早期発見・対応
- 患者・家族への継続教育
- 他療法への円滑な移行支援
患者さんとご家族へのメッセージ
腹膜透析は在宅で行える優れた治療法ですが、患者さんの状態や希望により最適な選択は異なります。医療チームと十分に相談し、自分らしい生活を送れる治療法を選択してください。
共同意思決定(SDM)の重要性
医療従事者と患者・家族が協力して、最適な治療選択を行いましょう
関連記事
透析方法の選択における共同意思決定
血液透析と腹膜透析を患者さんと一緒に考える重要性について
血液透析と血液ろ過透析の違い
HD・HDFの特徴と多発性のう胞腎患者への適応について